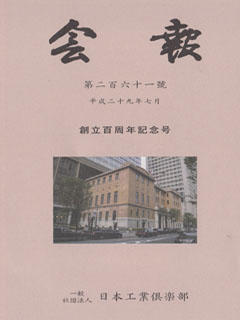先般、日本工業倶楽部の公開講演会で、藤原作弥氏から「昭和時代に学ぶ」というご自身の体験に基づいた生き方・考え方についての示唆に富んだご講話を拝聴した。
藤原氏は1937年生まれで、7歳の時にご家族で旧満州国モンゴル人居住区の興安街(現在のウランホト)に移住、終戦の直前に安東(現在の丹東市)へ逃れられた。
その安東で過ごされた1年余りにわたる抑留生活を関係者からの取材や現地往訪などで徹底検証された回想記「満州、少国民の戦記」(1988年、新潮文庫)を刊行されている。
同氏はジャーナリストとして時事通信社の記者・解説委員を36年間務められた後、日銀副総裁になられた高名な方であるが、満州での逃避行がその後の氏の生き方に多大の影響を齎したと自己分析しておられる。
満州から疎開して北朝鮮に留め置かれた日本人の惨状については、ごく最近に刊行された井上卓弥著「満州難民~38度線に阻まれた命」(2015年、幻冬舎刊)に詳述されていると、藤原氏から伺った。
著者は気鋭の毎日新聞記者で、満州から北朝鮮に逃れて辛酸を嘗めた生存者からの精力的なルポを積み重ねて、終戦とともに始まった悲劇を追求し、先の大戦の本質に向き合おうとする意欲的な作品を構築された。このようなノンフィクションの名著が戦後70年を経て出版されたのは驚きである。
筆者は1934年生まれで、新京(現在の長春)から一旦北朝鮮へ疎開して終戦を迎え、満州へ戻って、安東で1年間難民生活を送った。すんでのところで北朝鮮に留め置かれる難を逃れて、奇しくも藤原さんとちょうど同じ期間を安東で過ごしたのである。
この2冊の名著に触発されて、当時小学校の5~6年生であった筆者自身の満州難民としての70年前の記憶を呼び起こし、「一満州難民の体験記」を残しておきたいと思い立った次第である。
満州への渡航
私の父は満州国の建国大学助教授として1944年11月に新京へ単身赴任していた。その父の許へ祖母・母・妹2人の家族5人が京都から新京へ引越したのは、翌年4月の中旬であった。3月13・14日には第1回の大阪大空襲があって京都の空まで真っ黒な煙に覆われ、大阪に住んでいた祖父一家も焼け出された。
この大阪大空襲の影響で出発が少し遅れたが、当時、すでに始まっていた学童疎開には参加せず、4月中旬から始まる新京での小学校の新学期に間に合うようにと渡航を急いだ。
下関から関釜連絡船で釜山まで7時間半。関門海峡には米軍の潜水艦が出没し、関釜連絡船での渡航はすでに大変危険であった。現に、戦時中に就航していた関釜連絡船10隻のうち、敗戦時に残っていたのは興安丸ほか4隻のみであった。それでも、当時は内地よりも満州の方がまだしも安全ではなかろうかと、両親ともに判断したようである。
釜山から新京までは、朝鮮総督府鉄道と南満州鉄道が共同運航していた「ひかり」号で、947.2キロを21時間で結ぶ快適な旅であった。この直行便は1945年8月のソ連侵攻により、運行不能となって以来、現在に至るも復活していない。
新京駅に到着すると、駅頭で4頭立ての馬車に出迎えて貰ったのには驚いた。これは父の親友で満州国の高官になっておられた鶴氏の差し回しであった。
新京での生活
新京では建国大学の近くの南湖のほとりに建つ官舎に落ち着く予定であったが、未完成のため、大同大街の一筋東側で南湖に近い東安街(現在の岳陽街)にあった父の同僚の内海庫一郎先生(ご帰国後、北海道大学教授)のお宅の2階に居候させていただいた。
近くの東安小学校の5年生に編入入学し、目新しい満語を学んだりして、1学期は勉学一途に勤しむことができた。また、東安街のすぐ近くには都心には珍しい原生林があり、そこで探検ごっこをして楽しく遊んでいた。2009年に再訪した時には、町並みはすっかり変わっていたが、この原生林はその面影を留めたまま「動植物公園」として整備されており、感慨無量であった。
新京での5か月間は、内地とは打って変わって空襲もない穏やかな日々であった。その間、5月には父が国民兵として応召された(満州第84部隊に属し、終戦後には10月からシベリアに抑留されて、翌々年の5月に運よく日本へ帰還した)。
大異変は1945年8月9日未明、ソ連軍が日ソ中立条約を破棄して突如満州国境を越えて侵攻を開始したときに始まった。この日は満州在住の日本人には忘れられない日となった。10日の午前1時頃にはソ連空軍による新京空襲が始まり、ソ連機が炸裂させた照明弾の閃光で深夜の空が一晩中明るかった。新京には防空壕などの備えはほとんどなく、まったく無防備であった。
北朝鮮・宣川(ソンチョン)への疎開
8月11日の夜には、ソ連軍の大部隊があと12時間後には新京に侵攻してくるという情報が流れ、皇帝・溥儀をはじめ政府の中枢機能は逸早く朝鮮国境に近い「通化」への遷都を決めて移動した。
12日には日本人社会の組織ごとに南方へ避難する計画が立てられ、満鉄との交渉が始まった。
建国大学の職員119名の一団はようやく13日の午後に新京を出発する無蓋貨車に乗り込んだ。この時点では、客車や有蓋貨車はすべて出払っていて、無蓋貨車しか残っていなかったからである。鮨詰めの貨車で、身動きもできず、真夏のことゆえ焼き付くような暑さであった。
列車は臨時便の殺到で途中での長時間停車を余儀なくさせられながらも夜を徹して南下を続けた。安東・新義州を経て、翌々日の昼前に北朝鮮の「宣川」という町で、貨車から降ろされた。宣川で降ろされた途端に、日本の敗戦を知らされ、正午に小学校の校庭に集められて玉音放送を聞いた。難民としての集団生活が、この校舎から始まった。
この時の情景を詠んだ母の俳句が残っている。
トンネルの灼熱地獄無蓋貨車
疎開貨車降りて捕虜たり敗戦日
新義州と平壌まで200キロの京義線の沿線には大小の町々が連なっている。宣川は満州との国境の町・新義州から約80キロ南に位置する当時は人口2万人程度の小都市であった。満州から避難民を乗せた列車は、分散を図るために、町らしい駅に停車する度に列車が後部から数輌ずつ切り離され、偶々我々の一団が降ろされたのが宣川であった。結局、宣川で降ろされた満州からの難民は累計5,600名であった。
宣川(ソンチョン)から安東への脱出
8月9日に対日戦を開始したソ連軍は、満州に侵攻する一方、20日には北朝鮮をも制圧、暴行や略奪を繰り返し、工場設備に至るまで金目のものを本国へ持ち帰った。宣川の校舎にもソ連の軍人が現れ、腕時計などが奪われた。
建国大学の疎開団は新京への帰還方針を早々に決め、9月初には宣川を出発した。満州への帰還は北へ向かい日本からは遠く離れることとなったものの、結果的に建国大学のリーダーの決断は正解であった。38度線による南北朝鮮分割以前のこの時期での状況判断は難しかったが、満鮮国境は翌年の2月には閉鎖され、それ以降は38度線を徒歩で越えて帰国する途しか無くなったからである。
敗戦の年の冬の北朝鮮での出来事は戦後もほとんど報じられていなかったが、無政府状態下での難民の生活は悲惨を極め、秋のうちに満州へ戻ることができた我々は不幸中の幸せであった。
森田芳夫著「朝鮮終戦の記録」(1964年、厳南堂書店刊)によれば、北朝鮮は8月中旬以降に満州からの避難民約6万人を受け入れ、元々住んでいた日本人と併せて約40万人が留め置かれ、1年間に3.4万人が死亡したとされている。満州からの避難民を最も多く受け入れた都市は平壌2.2万人、次いで鎮南浦7.5千人、宣川5.6千人(越冬したのは1.3千人)となっている。避難民のうち、半年間に8割は満州へ戻った。
宣川は北朝鮮から38度線を徒歩で越えて引揚げた記録を題材にした藤原てい著「流れる星は生きている」(1949年、日比谷出版社刊)」の舞台にもなっている。新京から南へ逃げるために乗った列車が宣川駅でストップしてしまい、そのため藤原一家は宣川で1年間の避難民生活を送つた。その後、38度線を徒歩で越えて日本へ引揚げるまでの苦難に耐えての逃避行の情景をビビッドに綴った大作である。この作品はベストセラーとなり、のちに映画化されて大きな反響を呼んだ。
この物語では、宣川の町は「美しい町であった。教会の塔らしい洋館、学校か図書館のようにがっちりした建物、その下にきっちり並んだ人家は薄い朝霧の中に眠っている。四方山に囲まれた盆地の中に四角に置かれたようなこの町の中央をつらぬく一すじの川と、川を横切って山の間に消えている鉄道線路が妙に淋しい。」と描かれている。
安東(現丹東市)での1年間の生活
建国大学職員家族の一団は一路新京へ戻ったが、我々一家5人だけは北朝鮮との国境の町・安東で下車して、当時安東に住んでいた祖母の甥である波治家に寄寓することとなった。波治氏は若くして満州へ渡って実業家として成功を収め、4人家族で洋風の豪邸に住んでいた。新京へ戻っても身寄りはなく、むしろ不安であり、安東に留まった方が安心との母の判断であったであろう。
安東へもソ連軍が8月下旬に侵攻してきたが、国府軍(国民党政府軍)も同時に進出、行政の主導権は国府軍が握っていた。ところが、国共合作を解消して内戦に突入すると八路軍(パーロ)が急速に力をつけ、10月下旬には大挙して安東に入城、国府軍を放逐した。ソ連軍はこれを機に、略奪の限りを尽くした後に撤収した。八路軍には国府軍とは違って整然とした厳しい軍紀が徹底しており、ソ連兵のように暴行や略奪を働くこともなかった。八路軍進駐のお蔭で、安東の治安が比較的良好に保たれていたのは、邦人にはありがたかった。
母は生計の足しに日本人の資産家から放出される衣類などを闇市で立ち売りするマイマイ(売買)と称する仕事を手始めに、タバコや大福餅を仕入れて毎日街頭で売っていた。筆者も日本人学校は閉鎖されたので行くところはなく、一日中母の行商を手伝って過ごした。
商品を積み込んだ餅箱を襷掛けにして前に持ち、大きな声で「スイヨー、スイヨー」(誰要、要らんかね)と中国人に呼び掛けた。お客が「(イーガ・トールチェン)(一個多少銭、一個いくら?)と聞いてくれば「リャンカイチェン」(両塊銭)、「サンカイチェン」(三塊銭)などと答えた。当時使っていた中国語は全部忘れてしまったが、「三つ子の魂百まで」で、これだけは今でも鮮明に憶えている。
もう一つ記憶に残っているのは、虱を潰す日課である。同じ下着を着たままで、風呂にも入れないので、不衛生極まりなく、冬でも虱が繁殖した。噛まれると痒いので、下着の縫い目に沿ってびっしりとくっついた虱を両手の爪先を合わせて根気よく、まさに「虱潰し」を実践したのである。
安東は満鉄が経営した「満州の小京都」ともいわれた人口9万人ほどのこじんまりとしたきれいな佇まいで、北側に迫る鎮江山には桜、南側に拡がる鴨緑江畔には柳が多数植樹されて、当時は純日本風の風情を留めていた。唐の時代から東を安んずる土地という意味で「安東」と呼ばれていたこの街は1965年に「丹東」と改称された。
葫蘆島(コロトウ)への移動
日本への帰国が決まったのは、1946年の9月に入ってすぐであった。国際赤十字の働きかけで、安東を支配していた八路軍政府と奉天(現瀋陽)を占拠していた国府軍との間に日本人の本国送還について協定が結ばれ、9月下旬に安東を発った。当時、安東・奉天間280キロでは、八路軍と国府軍が戦闘中であったので、鉄路は破壊されて使えず、徒歩で踏破するしかなかった。戦闘は散発的で激しくはなかったものの、12月には国府軍が安東を再占拠、翌年に最終的に撤収している。
引揚げ隊は老若男女100人余りが一団となって野山を行軍し、夜は野宿した。盗賊に襲われたり、疫病に苦しめながら黙々と歩き続け、1か月近く掛けて奉天に辿り着いた。奉天から葫蘆島(現遼寧省葫芦島市)までは旅客列車で運ばれた。
博多への引揚げ
葫蘆島から博多までは米軍から提供されたリバティー型の輸送船に乗船、1昼夜の航海で博多港に上陸した。
10月下旬に博多に着いた時には、母が船内で転落して骨折したり、上の妹が長途の疲れで栄養失調に陥ったり、散々であった。このため上陸時に登録ができなかった故か、我々家族5名の引揚記録は厚労省に存在せず、引揚げ時期などの詳細は詳らかでない。
上陸時には、米軍が虱などの防疫対策として持ち込んだ有機塩素系の殺虫剤・DDTの白粉を頭から大量にぶっかけられて、窒息しそうになった。この記憶だけは、はっきりと脳裏に焼き付いている。
満州からの在留邦人の引揚げについては、1946年4月には国府軍の「日僑遺送」に対応する米軍司令部の日本人送還チームが、万里の長城が黄海に達する山海関からわずかの距離にある遼寧省の葫蘆島に設置された。
この米軍の支援で、終戦時に約155万人とされた満州在住日本人のうち約105万人が、米軍が調達した貨物船などでほぼ1年間間断なく葫蘆島から博多港ほかに帰還した。1956年の8~12月には延べ218隻の引揚船がピストル運航で葫蘆島から博多港に入港している。
「引揚げ」「引揚げ者」という役所用語は、敗戦時に満州・台湾・樺太など海外に住んでいた民間の日本人の帰国や帰国者を指す言葉として定着しているが、何となく違和感を覚える。
我々引揚げ者は、意気揚々と外地へ赴いた時とは逆に、終戦後は帰還の意思があって自主的に帰って来たのではなく、身も心もぼろぼろに傷ついて這々の体でやむなく帰国したのであり、元へ戻ったわけではない。
要するに、引揚げ者の実態は難民である。現に、旧満州では「奉天日本人難民収容所」が設置されたりして、中国側は在住日本人を難民として扱っていた。
遅きに失した恨み
「満州難民」として辿った私個人の実体験をおぼろげな記憶と若干の傍証を頼りに書き留めることで、さきの大戦の悲劇の一端を忘却の淵から多少とも引き戻すことができたのではないだろうか。
しかしながら、これは当時11歳であった子供の強烈なる記憶の一端に過ぎない。
3人の子供を抱えた母や祖母の苦労はいかばかりであったろうか。その悲惨さは想像に難くない。
せめて母の生前に聞き書きでもしておけばよかったものをと、後悔すること頻りである。
(元住友銀行専務取締役、元広島国際大学教授)
(2017年7月25日発行、日本工業倶楽部「会報」第261号「創立百周年記念号」p64~72所収)