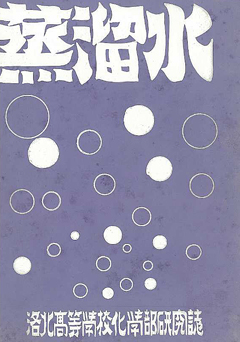
この一年間、化学を学んで来たのであるが、もし「化学とはどういうものなのか」とまた「何故に化学を学ぶのであるか」と聞かれると、ちょっといや大いにまごつかねばならない。そんなことは少しも考えずに、ただ漫然と学び、無理に憶えたにすぎないからである。化学を習い始めた時に、そういうことを少し深く考えておけば、もっと面白く、更に容易に化学を習得し得たのではなかろうかと今更悔いるほかない。
さて、化学はよく「バケ学」といわれる。「化物」「ばかす」の、また「変化」の「化」である。世の中は変化であり、絶えざる動きである。故に故人曰く「万物は流転す」と。化学において、その典型を見ることが出来る。化学はもともとヨーロッパで発達した学問で、英語で"Chemistry"の"Che"の音が中国で「化」と表され、それが江戸時代の終り頃にわが国に入ったということである。それ以前には、「舎密(セーミ)」という名で呼ばれていた。これは、オランダ語の音をとったものである。英語の"Chemistry"、ドイツ語では"Cheme"(ヘミー)、フランス語では"Chimie"(シミー)の語源は、よく分からないが、数千年前の古代エジプトの名の"Chem"(黒、黒土などの意味で黒土のエジプトを表すものと云われる)に因んだものといわれている。
古代エジプトでは金・銀・銅・鉄・錫・水銀などが用いられ、ガラス・硫黄・石灰その他のものも作られ、染色も行なわれていたので、エジプトの学問といったような意味合いであろう。化学はかくも古い昔に語源を持つ幾何学・天文学と並ぶ最も歴史の古い学問である。バケ学の応用によって、いろいろな物質が元のものとはまるで似ても似つかぬ物質に変えられるのであるから、「化」の名はこの学問の本質をよく表している。今日、ナイロンと呼ばれる「塩化ポリヴィニール」は、そもそも石灰石と石炭と水と食塩とが化けたものである。美しい染物に用いられる染料のほとんどが、黒い石炭を原料としている。
化学はどんな学問であるのか。もう少しはっきりつきつめて見よう。我々人間も牛や馬も洋服や靴も空気も水も星も自動車も、すべてこの世のあらゆるものは所謂「物質」から出来ている。化学はこれら自然のままの物質、あるいは天然のものに人工を加えて作られた物質の性質やその変化の仕方やその作り方などを研究する学問であるという説明を読んだことがある。物を物質として捉える点において、生命を持つ一個一個の個体を対象とする生物学と異なり、この物質というのは大きさと重量を有するものであって、手で把握することの出来ない電気や光や熱を主としてとり扱う物理とも区別される。
次に思うに化学には二つの面がある。その一つは、我々の日常生活に深い関係を持ち、その研究の結果が我々の生活の向上・改善に大きな働きをするものである。これは、応用化学呼ばれるもので、たとえば、非常に効き目のあるある薬を製造したり、丈夫で着心地の良い布地を作ったりする類である。二十世紀の三大発明として、まず原子爆弾、次いでペニシリンとナイロン・ビニロンなどの化学繊維が挙げられている。原爆は別として、後の二つは二十世紀の化学者が成した大発明である。この事実からも、化学が社会生活全般に如何に大きなウエイトを占めているかということは自からうなずかれる。
他の一面は直接日常生活とは関係を持たない理論(基礎)化学として、応用を離れて水やアルコールの性質を調べ、物質の変化する状態について研究するような分野がある。これがなければ、応用化学の充分な発展は望まれるものでない。今はやりの合成繊維のナイロンが製品として1938年に発売されるまでには、約10年間にわたるナイロン製造のためには直接関係のない基礎的な研究がアメリカのカロザースらによって行なわれたのである。ところが、現今では化学は基礎理論の時代を離れて専ら応用化学の時代に入ったなどといわれることをよく耳にする。これは資本主義のバックに押されて応用化学が目覚ましく発達したのに反し、それに先行すべきである基礎化学がやや遅れをとっているのではなかろうか。産業界のことは何も分からないながらも、そう感ぜられる。
先日、触媒に関する本を読んでいて気づいたことであるが、軍事上は火薬に、平時においては肥料として欠くことの出来ない原料のアンモニアがドイツで作られるようになった。そのアンモニア製造の接触法で使われる触媒は、いろいろな触媒になりそうな物質を数多く当てはめて見て最も効果的なものを探し求めた結果、偶然に得られたということである、他の工業においても同様で、それら触媒間に存在するであろう関係はいまだに分かっていない。暗中を模索して良さそうなものをとり上げるという、こう見ただけでは非常に非科学的極まる方法を採るより仕方がないそうである。
思うに自然科学に限らないが、どの学問でも学科でも打ち込んで研究すれば面白いものである。化学は学習の始めから面白い学問であった。一つには、それは我々の身のまわりにあるいろいろな物質や変化を相手にして研究するからである。ローソクの燃える理由について研究し、鉄のさびるわけを調べ、牛乳の性質や色素の染まりつくわけを研究し、インクや石鹸を作る。また、着物のしみを取ったり染色したりするのは、今日にも明日にも役に立つ。
先日、マーク・ゲインの「ニッポン日記」を読んだが、その中で次のような記述が興味深かった。志賀義雄が獄中にいた頃のことである。字を書いたものを差し入れる際には厳しい検問を受ける。そこで彼らは差し入れる本に澱粉を水に溶かして字を書いた本を差し入れ、獄中では怪我をしたと云ってヨードチンキを貰ってきてふりかけると、澱粉で書かれた字の部分だけが沃素澱粉反応で紫色に浮き出るという寸法である。後の処分は少々汚いが、小便をかけて流したそうである。獄中から連絡する際には、うどんや米から澱粉を製造するのである。このように化学の知識はというものは、思いがけない所で役に立つものである。
化学に限ったことではないが、天地万象あらゆるものに興味を持ち、その謎を明かそうとするのは、人類発生以来の本能である。学問というものは自然界に対する興味や疑問を持つことから発達したのである。その疑問や興味を明らかにしようと観察する際に、注意深くありのままに見逃さないように観察する態度が肝要である。このことは化学を学んで始めてつくづく感じとることが出来た。この態度は広く人生行路において出くわす諸問題を処理する際にも不可欠なものであろう。
1892年、イギリスのレーリ卿という物理学者は、空気からとった窒素の1リットルの重さが零度(摂氏)1気圧で、1.25718グラムであるのに、化学薬品を原料として作った窒素は1.25107グラムであることを知った。この0.00611グラムというわずかの差に注目して、空気中には窒素・酸素・炭酸ガスのほかにアルゴン・ネオン・ヘリウム・クリプトンなどそれまで知られていなかった不活性気体が含まれていることを発見したことは、有名な話である。しかし、もしネオンが発見されていないならば、美しい夜のネオン街は見られず、またヘリウムがなければ、安心して乗れる気球もできていない。
以上実際に有用な化学を見て来たのであるが、たとえ化学が少しも利用価値のない学問であるにしても、それを研究することにはやはり深い意義があると思われる。世の中にいろいろなものが散らばっているのは、ちょうど無数のガラクタが部屋の中にばら撒かれたようなものである。これを系統立てて整然と並べて見ようと思う本能的な精神が、自然科学、とくに化学や生物の分類学における科学というものの本質と見ることが出来るからである。
結果的には、やはり現実性を持たざるを得ないが、近代の化学で認められた多くの事実を整理・分類し、その結果から自然界に行われている所謂法則を発見する。さらに、その法則が何故に行われているかを説明する理論を考え出し、その理論はさらに事実によって確かめられ、次々と発展していく。このようなプロセスには、常に合理的なものの考え方一貫してとられている。合理的というのは、ある事柄が原因となって他の結果が出るという風な考え方である。
この合理的精神への転換は、18世紀末からの中世的な臭いの抜けきらない力学的自然観から新しい自然観へと、具体的には光の粒子説に代わる光の波動説、電波説に代わる電磁気の「場」の説、熱素説に代わる熱の運動説等の出現により行なわれた。その先駆をなして導いて行ったのが、ラヴァジェ・ダルトン・アヴォガドロらの一連の化学者であった。このような歴史的な意義を附加せしめることによって、旧くエジプトに始まり、近代の合理的科学思想の先駆をなした化学を学ぶことに、それだけでも離れ難い情念が湧いて来るのである。
(岡部 陽二)
(1952年7月1日、洛北高校化学部発行、洛北高等学校化学部研究誌「蒸留水」p12~16所収)
