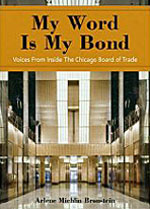
「きらめき」前号で「民主党の公開会社法に大いに期待する」と論じたが、そもそも「公開会社法」なるものは上場会社に限って適用されるルールであり、それであれば何も国会を煩わすことなく、証券取所が取引所規則として制定すれば済むことである。このルールに従わない上場会社には上場廃止を迫るだけのことであり、現に欧米ではそうなっている。
したがって、前号論説の真意は「民主党の公開会社法に期待せざるを得ないような東証の不甲斐なさに憤慨する」ということである。「公開会社法」が法制化の対象と考えているのは、①企業会計のあり方や株主質問権・回答義務の導入など情報開示の明確化、②独立社外取締役選任の義務化や従業員代表監査役導入などの適切な企業統治の実現、③企業集団を基本要素と認識し親子上場は厳しく規制するといった上場会社のみに限られたガバナンスについてである。
これらのルール化に東京証券取引所が自主的に取組むべきは当然であるが、それに加えて東証自体のガバナンスを確立することが急務である。見方を変えれば、東証のガバナンスが確立されないかぎり、上場企業に向けての適切なルール作りも期待できない。本稿では、このような視点に立って、東証に求められる意識改革とガバナンスのあり方について以下の諸点を指摘し、東証の奮起を促したい。
1、外国株式の上場と取引活性化
東証での外国株上場会社数は1991年末には125社あったが、その後は毎年減少して、2008年末では16社となっている。外国株の年間売買高も2008年度は7億ドルと10年前とまったく変わらず、要するに、東証では外国企業は完全に無視されている。
外国株の上場を、他の取引所と比較すると、下表カッコ内のとおり、ニューヨークとロンドンでは上場会社数・売買高ともに10年間で大幅に増加している。ドイツ証券取引所では、上場会社数は減少しているものの、売買高は10年間に5倍に増加、2008年には5,000億ドルに達している。
東証は年間売買高で昨年は上海取引所に抜かれた。国内で有り余っている過剰貯蓄にとっての投資の選択肢を拡充させ、アジアの成長分野への資金供給の面で相応の役割を担うには、外国株式などの商品ラインアップの幅を広げ、こうした資金の仲介を円滑にすることが東証にとって重要である。

ところが、残念ながら、東証にはそのような問題意識は皆無である。東証が国内証券会社の集合体であり続け、彼らの営業姿勢が上場企業の方を向いている限り、投資家が望む金融商品の品揃えに注力するという発想は出てこない。日本株が魅力を失っているなら、魅力の大きい外国株を投資家に推奨し、その売買を円滑化するために外国株の上場に積極的に取組むという目的意識をどうして持たないのか不思議である。それとも、そのような期待を抱く方がおかしいのであろうか。
2、ベンチャー企業向け新興市場の抜本改革
東証マザーズが改革と称してとり始めた新しい上場・上場廃止基準は、新規上場企業の成長性は重視せず、むしろ老舗企業をとり込んでいこうという姿勢が伺え、真の新興市場からは撤退の方針と見られる。東証もロンドン証取のAIMと連携してプロの投資家を中心とする新興企業向けの新市場を創設する方針は打ち出している。斎藤惇社長就任時には、①財務諸表は英語でよく日本の会計基準に準拠しなくてもよい、②四半期決算も要求しない、③引受証券会社は上場後も責任を持ち続けるといった新しいベンチャー企業向け市場を目指すと具体的に宣明されている。ところが、社長就任後2年半を経ても、これらの改革は何一つ実現しておらず、この計画はすでに画餅に帰している。有言不実行の典型である。東京資本市場を活性化し国際的な信認を高めるには、斎藤社長が掲げられているような改革を着実に積み上げていくことで必須であるが、今の東証にこれを期待することはできない。
3、誤発注処理の不手際に象徴されるITシステムの遅れ
本年初から稼働し始めた新売買システム「アローヘッド」は、注文処理時間を5ミリ秒と欧米並みに短縮したもので、一日の出来高1.2兆円程度の東証には十分な高性能と説明されている。この新システムが、経営戦略としての情報システムとして運用上のソフト面も含めて誤発注などにも機敏に対応し得るものであるのかどうか、海外の先進取引所のシステムに比して機能的に遜色がないかどうか、今後の実績を見守るほかない。
それにしても、みずほ証券が一瞬にして415億円の損失を蒙ったジェイコム株誤発注事件は、発注側にも責任があるのは当然ながら、このような場合の危機管理を事前に想定もしない欠陥システムを検収して運用していた東証の責任も重大である。裁判の場で「東証は取引の場を提供するだけで、取引上のトラブルには責任を持たない」と厚顔無恥な主張を繰り返していたのにはただただ呆れるばかりである。
4、東証自体のガバナンス強化
東証は早期上場を目指して、持ち株会社を設立、取引所と自主規制法人を分離して、社外取締役中心の委員会設置会社の体裁を採っている。しかしながら、運営の実態は執行役員による旧来通りの経営スタイルと見られる。なかでも問題は、社外取締役11名中に投資家サイドの代表者を一人も入れていないので、証券取引の一方の当事者である機関投資家や個人投資家の意向はまったく反映されない組織となっている点である。
一例ではあるが、東証は場立ちによる対面取引が行なわれていた立会場がコンピュータ化により不要となったために、この空間を投資家に対してリアルタイムの市場情報を提供し、上場企業に対しては的確な情報開示をサポートする場としてする場として活用している。200名近く収容できるホールも備えた「東証Arrows 」を開設し、見学会や上場会社説明会なども開催されている。しかしながら、当協会のような投資家団体には会場の使用を認めず、情報発信は東証発のものに限定されている。
立会場が不要となった変化への対応も疑問である。1972年に豪華な立会場をスレッドニードル街に建設したロンドン証取は、コンピュータ化の完成後、2004年にいち早くこれを売却して、セントポール寺院裏手の貸しビルに移っている。これが、合理的な経営判断であろう。
ロンドン証取で生まれた"My Word is my bond"(私の言葉は私の契約である)という信念を東証の経営者にも切に期待したい。
(日本個人投資家協会理事 岡部陽二)
(2010年1月15日、日本個人投資家協会発行機関紙「きらめき」2010年1月号所収)

